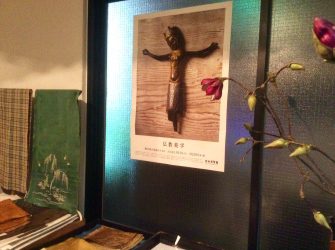
二月の店内
二月は草木の芽が張る「草木張月」という美しい別名があります。木々たちの様子に変化がみられ、その枝先に色を含んでくるようになるのが二月の頃です。道々の冬枯れの草と土との間には、いろいろな草が小さな緑の葉を広げており、たんぽぽも踊子草もみられます。今は三月が目前で、陽の光もずいぶんと力が増してきました。二月の初めごろに感じられる辺りに漂うひそやかな春の兆し、そうした大気はもう薄れてしまったように思われます。これから春が動きだし、春酣の花の季節がはじまります。
今月もありがとうございました。ホームページの営業日カレンダーを御覧くださり、御来店いただけますこと、心より感謝申し上げます。お客様のお探しの裂のことや、次にお作りになるお仕覆のイメージについてなど、店でいろいろとお伺いさせていただき、お持ちいただきましたお道具と裂を取り合わせてお客様とお話をさせていただくこと、私もとても勉強させていただいております。裂も骨董ですので、出会わないと私も裂と出会えないのですが、味わいのある古い裂をご案内させていただけますよう、いろいろと探してまいりたいと思っております。
来月もまた、どうぞよろしくお願い申し上げます。



